ルールに関する質問・議論スレ~100
| sharp | |
| 登録日:2017/10/27 01:57最終更新日:2017/10/27 12:23 |
コメントを書く
このスレッドはコメントがいっぱいになりました。
新たに書き込みを行う場合は新しいスレッドを立ててください。
コメント一覧
| 40. sharp | |
| 2017/11/29 00:30 |
> 禄存さん はい、ほとんどのダメージを上昇させる忍法にはそう書かれているのですがね。 忍獣である忍鮫が持つ忍法【ジョーズ】にはその記述がないのです。 【開祖】によって名前を【接近戦攻撃】に変えた、複数種のダメージを与えられる忍法を使用する際、 【獣技】により【ジョーズ】を適用した場合はどのような処理を行えば良いのか、という話でした。 恐らく「こうするべきだ」という答えが出せない(他のアプローチをかけようにも似た例がないため)と思われるため、 GMは下で挙がったようなオリジナルの裁定を行うのが良いんじゃないかな、という次第です。
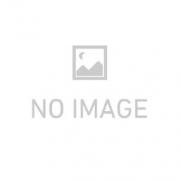 | 39. Rokuryoku |
| 2017/11/28 22:33 |
原則的にダメージの上昇は 忍法の最初に書いてある攻撃方法のダメージだけが上がります。帝釈天なら接近戦 使役術なら集団戦のダメージが上がります。
| 38. sharp | |
| 2017/11/28 18:19 |
>サユタさん ふむふむ。 平和的に解決するとしたら、おっしゃる通り、 ・もともと与えられるダメージ種の中から2点分選んで上昇させる もしくは、 ・その攻撃忍法の分類(効果欄の最初に書いてあるもの)に応じた種類のダメージを2点上昇させる といったところでしょうね。 とはいえそのように処理するよう書かれているわけではないので、 いずれにせよオリジナルの裁定が必要になるのかな? ここで面倒な目で見てしまうと、「忍法のダメージ」は「忍法の(合計の)ダメージ」ではなく、「忍法の(効果に書かれている)ダメージ」と取れてしまうのでは?ということからの今回の疑問です。 仮に取れるからと言って、このように処理するGMは多くはないとは思いますがw
| 37. サユタ | |
| 2017/11/28 17:25 |
>sharpさん 私見ですが ・上昇するダメージの種類が書かれていない ということはダメージを区別しないで処理するということではないでしょうか。 【帝釈天】が与えるダメージは接近戦ダメージ1点・射撃戦ダメージ1点・集団戦ダメージ1点の計3点。 この3点を2点上昇して計5点のダメージが発生します。 その内訳は忍法効果に記載されている各1点にプラスで 上昇分の2点をどこに処理するかですが、 他の忍法の場合は「最初に書かれているもの」と指定があるので、 指定がない今回の場合、【帝釈天】で与えられるダメージの 接・射・集のどれかに自由に振り分けられるという考えです。 他の忍法で例えるなら【使役術】の場合などは射・集に振り分けられますが、 そもそも発生しない接近戦ダメージは上昇しないという処理になるかと。 いずれにしても「【接近戦攻撃】のダメージを2点上昇」という原文から 「発生源の合計ダメージを2点」上昇させる効果と解釈します。 >【帝釈天】にこの効果を適用した場合、 >接近戦ダメージ・射撃戦ダメージ・集団戦ダメージをそれぞれ3点ずつ与える という処理では結局合計で「【帝釈天】のダメージを6点上昇」させてしまうからです。 「【接近戦攻撃】の各ダメージを2点上昇」や「【接近戦攻撃】のすべてのダメージを2点上昇」 という表記の場合のみ、接・射・集ダメージをそれぞれ別ものとして上昇させることができるかと思います。
| 36. sharp | |
| 2017/11/28 12:52 |
>marieさん あー、そもそも修得できない可能性ですか。なるほど、どうなんでしょうね。 同名の忍法を「修得する」ことはできませんが、 同名の忍法を「修得している状態である(複数所持)」こと自体はルールに抵触しないと思われます。 勝手な命名ですが、下の「TCG的効果適用」において、【開祖】が未修得になった場合などに同名の忍法を2つ修得しているという状況が生まれますしね。 「ルール効果適用」においてはその限りではありませんが。 【開祖】という忍法を考えると、キャラメイク・リスペック時の忍法の修得もあきらかに同時ではありません。 つまり、【開祖】によって後天的に同じ名前の忍法を「修得している」状態になりましたが、既に所持しているものと同じ名前の忍法を「修得する」タイミングは存在しなかったので、ルールに触れるタイミングはなかった、という感じです。 まぁそうでなくとも、【特別教室】によって【接近戦攻撃】を失った後に【開祖】を得るというシチュエーションもありえますので、 どちらにせよ【ジョーズ】の効果の他忍法への適用については考慮すべきかと。
| 35. marie | |
| 2017/11/28 09:04 |
>sharpさん 開祖でも「接近戦攻撃」は修得できないという処理になるのではないかと思います。 「接近戦攻撃」は複数修得することが認められているため、本物の「接近戦攻撃」は複数修得できます。 しかし、開祖で「接近戦攻撃」に変えた忍法からすれば、効果として複数修得が認められていないため、同名忍法の複数修得に当たるのではないでしょうか。 つまり、「接近戦攻撃」側からしてみればセーフでも「接近戦攻撃(開祖)」からしてみればアウト、ということです。
| 34. sharp | |
| 2017/11/28 08:27 |
【獣技】で思い出したのですが、忍鮫の忍法である【ジョーズ】について。 この忍法、【接近戦攻撃】のダメージを2点上昇させるのですが、 ・上昇するダメージの種類が書かれていない ・上昇するダメージは最初に書かれているもののみである記述がない ・忍法の分類(流派忍法・妖魔忍法など)がない という特性を持っています。 まぁ普通に考えれば【接近戦攻撃】のみにしか適用されないので問題はないのですが、 【開祖】によって他の忍法の名前を【接近戦攻撃】にした場合は話が変わってきます。 例えば【帝釈天】にこの効果を適用した場合、接近戦ダメージ・射撃戦ダメージ・集団戦ダメージをそれぞれ3点ずつ与える、という処理になるのではないでしょうか?
| 33. サユタ | |
| 2017/11/27 21:47 |
>>marieさん >>枯れたもみじさん ご回答ありがとうございます。 質問1は対象を取らないので対抗されないということですね。 質問2,3はmarieさんの回答がしっくりきますね。 やっぱり「同じシーンに登場しているキャラクターが【生命力】を失ったときに使用できる」は シーンに登場していないと使用できないってことですよね・・・ 獣技・猫の道に絶対防御打ちたかったけどダメかw
| 31. marie | |
| 2017/11/27 21:20 |
1,魔法について(p142) 基本ルルブでは「目標が存在しない奥義は、対抗できません」としています。 「目標が自分」という状況が発生するならば、全ての奥義に目標が存在することになるため、この注意書きは必要のないものとなります。 そのため、「不死身」「完全成功」は目標が存在しない奥義であると思われます。 2,奥義「絶対防御」の使用可能タイミングについて(p38) 「絶対防御」の使用はルルブによれば「同じシーンに登場しているキャラクターが【生命力】を失ったときに使用できる」とされているため、使用するためには使用したいタイミングでシーンに出ている必要があります。 「シーンに出ていない自分」に対してはGMの判断に委ねられますが(主にシーンへの途中参加について)、「シーンに出ていない他PC」については使用できないとするのが妥当かと思います。 3,その場合の奥義情報および奥義破りの判定について(p69) この場合、奥義情報は同じシーンに登場しているPCに渡ります。 また、奥義破りは同じシーンに登場していなければ行なうことは出来ません。 ルルブの記述通りならこんな感じかと。